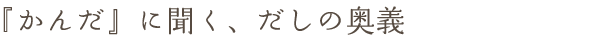
手のひらに伝わる椀のぬくもり。熱々のすまし汁の中に美しく盛られた季節の椀種。そして立ちのぼる柚子の香。もてなしの心が凝縮された一杯の椀は、日本料理の華ともいわれる料理だ。その味の基本になるのが「だし」。昆布と鰹節から引いた「一番だし」が、椀の命である。
60〜61ページの料理8種は、東京・元麻布の日本料理店『かんだ』の献立。一番だしを使った椀ものと、二番だしを含ませた煮物など、だしをベースにした日本料理の一例を作ってもらった。上段4品が一番だし、下段4品が二番だしを使った料理である。
主として吸い物など、椀ものに使われるのが一番だし。クセのないうま味だけを抽出した贅沢なだしだ。
それに対して、昆布のうま味、鰹節の香りなどを、しっかりと煮出したのが二番だし。こちらは煮付けや雑炊、お浸し、炊き込みご飯、和え物など、様々な料理に使われる。だしが、その料理店の味を決めると言っても過言ではない。
料理人にとっては秘中の秘ともいえるだしの奥義を、「かんだ」主人、神田裕行さんに聞いた。
「僕の味のキーワードは“淡”です。だしは濃くとればいいと思っている人がほとんどですが、日本料理の場合は濃いことが美味しいことではなくて、バランスの良いことが美味しいことなのです」
神田裕行さんが引く一番だしは、限りなく湯に近い。だからこそ、椀種の持つ繊細な味を生かし切ることができるのだ。羅臼昆布、本枯節など、極上の素材を使いながら、その上澄みともいえるエッセンスだけを抽出する。食材の主役は椀種だが、切れの良いうま味の上品なだしは、「かんだ」の料理の、もうひとつの主役とさえいえる。
とはいえ、基本的にだしは黒子である。椀もののだしの役割は、うま味だけを準備すること。それもだしの存在を感じさせずに。一番だしの控えめなうま味に、椀種の味と香りが加わって、吸い地は初めて完成する。鰹節の香りが強く出過ぎて、吸い物がカツオの味や香りになってしまったら、これはいくら美味しくても失敗なのである。
だしと椀種に加えて、もうひとつ重要な要素がある。それは塩分だ。適度な塩分が、だしのうま味を強める働きをする。試しに一番だしを小皿にとって味見してみても、普通の人にはうまいとは感じられない。そこに適量の塩をひとつまみ入れると、とたんに人間の舌は、この液体を美味と感じるようになる。
バランスのとれる塩加減というのは、実は厳密に決まっていて、血液に近い濃さだといわれている。美味しいお吸い物の塩分が、ほぼそれに相当する。塩分が多すぎると、体が吸収するときに水を飲んで薄めなくてはならない。濃くもなく薄くもなく、そのままストレートに体が受容できる塩加減を、舌は美味と感じるのだろう。ただし、ここに油脂などが介在すると、美味と感じる塩分量は大幅に増加する。濃いだしや、油脂の加わったスープなどの味のバランスを整えるには、多量の塩を必要とするのだ。
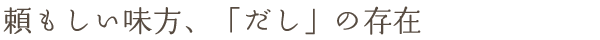
「だし」は、日本料理特有の技術である。フランス料理のフォンや中華料理の湯なども、うま味を多く含んでいるが、同時に油脂や膠質なども含んだ液体で、日本のだしとは見た目も使い方も異なる。水に、うま味と香りだけを抽出した「だし」を使うような調理法は、日本以外の国には見つける事ができない。
野菜や魚などの食材がもともと持っている繊細な味わいを生かしたいと思ったとき、だしは頼もしい味方となる。湯に近いほど薄い味なのに、料理に決定的な影響を与える。日本料理は、だしの存在なしには成立しない料理とさえいえる。
さて、そのだしを引くために使われる最も一般的な食材は、昆布と鰹節だが、なぜこのふたつなのか。日本料理と昆布、そして鰹節の歴史をたどって、千年を越える時間を遡ってみよう。

古代日本の基本法令『養老律令』が施行された養老2年(718)ごろには、すでに「煮堅魚(にかつお)」と呼ばれる鰹節の原形ともいえる食品が存在していた。これは切った鰹を煮て干した加工品で、当時はだしを引くという使い方ではなく、刃物で薄く削いで、それを食していたらしい。
この時代、日本列島の沿岸部には小魚も多く、黒潮に乗って回遊するカツオの群れが小魚を狙って、海岸線のすぐ近くまで押し寄せていた。
身肉にうま味が豊富で魚体も大きなカツオは、魅力的な食料だ。当時の人々は、これを捕獲して、比較的日持ちのする煮堅魚などを作った。こうしたカツオの加工品が内陸部に運ばれ、都人の食膳を賑わした。煮堅魚などの奉献を記録した当時の木簡が、現在の平城京跡から多数出土している。
平安時代以前の日本料理は、食卓に調味料が置かれ、料理に自分で調味して味わうという食べ方が主流であった。だしはまだ利用されていなかったと考えられている。
普及し始めた当初の鰹節は、公家の人々にとっては美味しい食材のひとつに過ぎなかったが、同時期の武士にとっては兵糧としての意味あいが大きく、戦時に命を繋ぐ貴重な食料として珍重された。
時代が下ると、煮堅魚の製法に改良が加えられ、うま味を濃縮する技術も進んでいく。“花鰹”の名が初めて登場するのは、室町時代の料理書、長享3年(1489)の『四条流包丁書』。花鰹というのは、鰹節を削った、いわゆる削り節で、色が赤みの強い褐色を呈しているものをいう。花鰹と呼ぶにふさわしい赤い色が出るのは、鰹節の製造工程で、火と煙でいぶして乾燥させたものに限られる。つまり現在の荒節に近い、硬くてうま味に富んだ鰹節が、この時期には完成されていたのだろう。
このように、室町時代から江戸時代前期にかけて盛んになった本膳料理の時代に、だしを使う調理法は普及していったと考えられる。
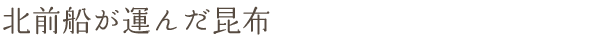
鰹節と並ぶ大切なだしの材料、昆布だが、その歴史は奈良時代以前にまで遡る。確認できる記録で“昆布”の文字が最初に現れるのは、奈良時代の出来事が記された、延暦16年(797)の『続日本紀』だ。霊亀元年(715)に蝦夷から朝廷に昆布が奉献されたことが記録されている。
昆布はほとんど北海道でしか採れない海藻なので、当時入手できるのは一部の権力者に限られていた。食品というよりも薬であり、奈良時代は黄金と同じ重さで交換されていたという。
それを一般の人々にまで広く普及させるきっかけとなったのが、大陸から伝えられた仏教の精進料理だった。精進料理は日本においては、国内事情にあう日本式の食事が工夫され、大陸にはなかった日本独自の食材、昆布が利用された。植物性の食材を美味しく食べられる調理技術は禅宗とともに広がり、信仰篤い一般の人々にまで普及していく。
北海道で採れた昆布は、日本海を航行する廻船で運ばれた。江戸時代には北前船と呼ばれる船である。和船は船底が平たい構造で、シケに弱い。太平洋は波が荒く、とくに房総半島沖の海域は海の難所だった。そのため廻船は太平洋のルートを避け、比較的波の穏やかな日本海を航行した。小浜、敦賀の港に陸揚げされた昆布は、琵琶湖の水運などを利用して京都に運ばれ、日本料理を完成に導いたのである。
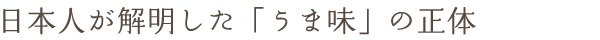
だしの説明をするときに、「昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸がうま味成分で、それを併用すると、うま味が増す」ということが良く言われる。わかったような気もするが、この説明だけでは、やはりよくわからない。味を言葉で伝えることは簡単ではないが、ここでは、もう少し詳しく、だしの持つ力を科学という視点を借りて検証してみたい。
だしの本質は「うま味」だが、この概念は長い間、欧米の学者には認められずにいた。味には五味がある。酸っぱい、苦い、甘い、辛い、それに塩辛さが加わるのが、古くからの中国の考え方である。これらの判りやすい味に比べれば、「うま味」はたしかに判別が難しい。しかし、実際には料理の現場で、世界各地の人々はそれと意識せずにうま味を引き出して利用してきたのである。前述のフォンや湯、そのほか魚醤や味噌などにも、多量のうま味が含まれている。
うま味物質の存在が科学的に証明されたのは明治41年(1908)のこと。東京帝国大学(現東京大学)教授の池田菊苗氏が、昆布の中から、うま味成分のグルタミン酸を発見した。池田菊苗氏は京都の出身で、奥様が毎日、昆布だしを使って料理を作った。その味が良かったので、池田氏はなぜこんなに美味しいのだろうと興味を持ち、研究したのだという。
それから5年後の大正2年(1913)、池田菊苗氏の弟子であった小玉新太郎氏が、鰹節のうま味成分イノシン酸を発見。次いで昭和35年(1960)には国く に中な か明あきら氏が、干椎茸のうま味成分、グアニル酸を発見した。国中明氏はグルタミン酸に、イノシン酸やグアル酸を合わせて使うと、うま味の効果が飛躍的に高まるということも突き止めた。経験から編み出された「昆布と鰹節」「昆布と干椎茸」という組み合わせが、科学的にも証明されたのである。
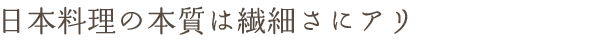
昆布や鰹節に、うま味がたっぷり含まれることはわかったが、では実際の料理において、それはどのように利用されているのだろうか。
従来の調理法では、昆布を水に浸し、沸騰寸前まで加熱する抽出方法が一般的だった。それが最近の研究で、最も効率的な方法は、60度の湯に1時間浸すことだと解明された。もちろん、だしの引き方は料理人によって微妙に異なるが、神田裕行さんは昆布だしの引き方を、次のように言う。
「一番だしの場合、水に昆布を入れ、夏は1時間、冬は2時間ほど置きます。70度以上に熱すると、粘りや好ましくない成分が出てしまうので低温抽出がベスト。うま味が出たら昆布を引き上げ、だしを火にかけます。30秒間沸騰させて水中の酸素を飛ばすと、後から入れる食材の、酸化による味の変化が防げるのです」
昆布から出る“好ましくない成分”とは、粘質物のアルギン酸や、アクの原因となるミネラル類などを指す。これらの味は雑味とも呼ばれるもの。繊細な味わいを追求する日本料理では、雑味はすべての努力を台無しにしてしまう。つまり、だしを引く時間と温度を適切にコントロールして、昆布のうま味だけを引き出すのが、料理人の腕の見せ所なのである。ところで、神田裕行さんの二番だしの引き方は、人とはちょっとだけ違っている。通常、二番だしは一番だしで使った昆布と鰹節を、もう一度加熱して煮出すものだが、「かんだ」では二番だしも、新しい昆布と鰹節を使って引く。一番だしに使った材料は、あれば鍋に加えるという程度の扱いで、とくに執着しない。二番だしの重要性をどのように捉えているかが、このことで判るだろう。
日本料理は、うま味に始まり、うま味に極まると言い切って間違いない。神田裕行さんが、自分の料理のキーワードは"淡"であると語ったひとことは、いみじくも日本料理の本質を衝いた言葉なのである。
 
主人の神田裕行さんは徳島の生まれ。「僕の料理は柑橘(かんきつ)の酢を多く使うところが特徴です」と語る。徳島はすだちの一大産地。子供のころから食べ物にすだちをかけると美味しくなることを経験してきた。自分が本当に美味しいと感じるものを、客にも味わってもらいたいという。パリの割烹、徳島の『青柳』で修行。東京・赤坂の『日本料理basara』の料理長を務めたのち、平成16年に自身の店『かんだ』をオープン。 |
|

